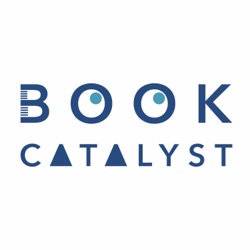Avsnitt
-
今回は、えむおーさんをゲストにお迎えして、宇野常寛さんの『庭の話』をご紹介いただきました。
タイトルだけではなかなか伝わってこない、本書の魅力についてたくさんお話いただきました。
書誌情報
* 出版社
* 講談社
* 出版日
* 2024/12/11
* 著者
* 宇野常寛
* 目次
* #1 プラットフォームから「庭」へ
* #2 「動いている庭」と多自然ガーデニング
* #3 「庭」の条件
* #4 「ムジナの庭」と事物のコレクティフ
* #5 ケアから民藝へ、民藝からパターン・ランゲージへ
* #6 「浪費」から「制作」へ
* #7 すでに回復されている「中動態の世界」
* #8 「家」から「庭」へ
* #9 孤独について
* #10 コモンズから(プラットフォームではなく)「庭」へ
* #11 戦争と一人の女、疫病と一人の男
* #12 弱い自立
* #13 消費から制作へ
* #14 「庭の条件」から「人間の条件」へ
倉下の感想
帯に「庭」と「制作」の文字があったので、「庭をつくる」という話かなと勝手な先入観を抱いていたのですが、どうやら違ったようです。
まず「庭」について徹底的に考え、「庭」の限界性すらも考えた上で、「制作」へと至る。そのような議論のダイナミズムがある本なのだと理解しました。
倉下自身も、昨今のインターネットの(わりと悲惨な)状況と、自分の手で何かを「つくる」ことの意義を重ねて考えていたので、本書はぜひとも読んでみたいと思います(すでに買ってあります)。
なんにせよ、現代では「どう生きるのか」という絶対的な指針が喪失しつつあるわけですが、本書はそれを考える重要な一冊になりそうです。
This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit bookcatalyst.substack.com/subscribe -
今回は、倉下が『エスノグラフィ入門』を紹介しました。
倉下のこれからの本の書きかたについて、消しきれぬインパクトがあった一冊です。
目次
はじめに第1章 エスノグラフィを体感する第2章 フィールドに学ぶ第3章 生活を書く第4章 時間に参与する第5章 対比的に読む第6章 事例を通して説明するおわりに――次の一歩へ
本編で読み上げるのを断念した「最終的な説明」は以下です。
エスノグラフィは、経験科学の中でもフィールド科学に収まるものであり、なかでも[* ①不可量のもの]に注目し記述するアプローチである。不可量のものの記述とは、具体的には[* ②生活を書くことに]よって進められる。そして生活を書くために調査者は、フィールドで流れている[* ③時間に参与する]ことが必要になる。こうしておこなわれたフィールド調査は、関連文献を[* ④対比的に読むこと]で着眼点が定まっていく。そうしてできあがった[* ⑤事例の記述を通して]、特定の主題(「貧困」「身体」など)についての洗練された説明へと結実させる。
これが具体的にどういうことなのかを一つひとつの章を通り抜ける中で確認していく形式になっています。
収録時に倉下が見ていた読書メモは以下のページで確認できます。
◇ブックカタリストBC110用メモ | 倉下忠憲の発想工房
エスノグラフィとは
エスノグラフィとはそのまま訳せば「民族誌」で、人類学で発展してきた手法が社会学でも使われるようになっているようです。
倉下が一番注目したのはその手法が「生活を書くこと」に主眼を置いている点。"革命的"なものって派手で注目されやすいのですが、それでも私たちの人生の大半を構成しているのは間違いなく生活です。「地に足のついた」という表現で意識されるのも、生活(感覚)との接続でしょう。
人びとの生活のディティールを描くこと。それはごりゅさんがおっしゃられたように小説(文学)との営みとも重なってきます。そこには、人の「生」を考える上で決して捨象してはいけないものが含まれているといっても過言ではありません。
倉下はいわゆるライフハックな話題が大好きですが、結局それも「人生」=「生活」がその基盤にあるからです。日々の生活から考えること。日々の生活を判断の基準にすること。派手なものに目を奪われやすいからこそ、むしろそうしたものにより注意深く視線を向ける必要があるのではないかと考えます。
自分の仕事にひきつけて
もう一点、自分の仕事に引きつけて考えたときに、「大きな方法」に注目するのではなく、むしろ日常にあるさまざまな小さな方法とそのディティールに注目する方が、実は「役に立つ」のではないかと考えることができるようになりました。
ときどき思うのです。大上段で理論を打ち立てるノウハウが、その語りの中で自分の方法以外をすべて「役立たず」だと切り捨てているのって何か変ではないかな、と。純化された理論に説得力を持たせるためには必要な修辞なのでしょうが、実践は(つまり日常は)さまざまに雑多なもので満たされています。そうした場面において、純粋な理論は参考にはなっても、そのままの形で適用できるものではありません。
だからこそ、むしろディティールの語りからはじめ、そのディティールを通して何かしらの理論にアクセスすること。その順番が大切ではないかと思います。なぜなら、そのようにすれば一つの理論に回収できないものが雑多な形で残ってくれるからです。
昨今のノウハウ書のあまりにもthinな感じは、整合的に整えようとしすぎたあまりに、実践の中にある雑多さを悉くそぎ落としてしまった結果ではないか、なんてことを考えています。
This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit bookcatalyst.substack.com/subscribe -
Saknas det avsnitt?
-
面白かった本について語るPoadcast、ブックカタリスト。
今回は、『脳と音楽』について語りました。なんだかんだ、音楽シリーズはこれで3回目くらいになるでしょうか?
BC076 『音律と音階の科学 新装版 ドレミ…はどのように生まれたか (ブルーバックス)』 - by goryugo
BC087 『音楽の人類史:発展と伝播の8億年の物語』 - by goryugo - ブックカタリスト
そもそも世間一般で「音楽の本」なんてジャンルの比率がけっして多くないことを考えれば、圧倒的に偏ってます。
でもまあ、ブックカタリストは「面白かった本」を語る場です。
ごりゅごの好みが音楽に偏っていれば、そういう本を面白いと感じるのは当然。それこそが「らしさ」だと思います。
で、そういうことを踏まえての今回の本ですが、とにかく興味深かったのが「音」の研究は「心理学」であるという観点でしょうか。
今回の話に限って言えば、離した内容の大半は人体の仕組みに関する話ですが、次回話そうと思ってる「音」の話って、その音に対して人間がどう感じるか、というもの。
これ、やっぱり確かに心理学です。
そして、今回学んだ内容は、どストレートではないんだけど、自分の音楽能力アップ、というのに確実に役に立ってくれています。
たとえば今回の話とかだと「高い音は、確かにわざと半音でぶつけること、するよな」とか。こういうのが、音楽の知識ではなくて「脳科学の知識」という観点からも理解ができる。
大抵の音楽やってる人とか、たぶんこういうことには興味がないと思うんだけど、自分的にはこの科学や人文学の知識と、音楽的な知識の両方が繋がるということが、とても楽しい。
今年一番最初に読み終えた本なんですが、いきなりこれは「今年一番面白かった本」になるかもしれない。そんなことも感じています。
今回出てきた本はこちらで紹介しています。
📖ブックカタリストで紹介した本 - ナレッジスタック - Obsidian Publish
This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit bookcatalyst.substack.com/subscribe -
今回は『「学び」がわからなくなったときに読む本』を取り上げました。
7つの対談が収められたすべての章が面白いので、今回は各章から話題をピックアップし、ごりゅごさんと話し合いながら進めるといういつもと違った形を採用しております。
おそらくこのポッドキャストを好きな方ならば、「学び」がたくさんある本だと思います。
あらためて「学び」について
というような感じで、私たちは日常的に「学び」という言葉を使っています。上記のように「学びがある」という形が多いでしょうか。
その言葉のニュアンスを探るなら、「有益な知見が得られた。示唆に富む内容だった」あたりでしょうか。素晴らしい体験です。
でも、おそらくそのままでは知識が増えただけです。ネットワーク的に言えば、どこかのノードに子どものノードが一つか二つ増えただけ。ネットワーク全体の組み換えなどは起きていないでしょう。
言い換えれば、すでに自分が所有している文脈に引きつけて情報を理解した、ということです。
それ自体はまったく問題ありません。問題は、そこからどうするのか、です。
* 関連する情報も探りまくる
* 似たような問題を考えまくる
* 実際に自分でやってみまくる
何らかの心情に突き動かされて、そういうことをやってみる。時間と手間をかけてみる。他の人からみたら、「なんでそんなに熱心にやっているの?」と思われる(あるいはあきれられる)ことをやってみる。
そうすると、単に知識がインクリメントされるのとは違った経験がやってきます。考え方や物の見方そのものが変質してくるのです。『勉強の哲学』は、その一次的な変化を「キモくなる」と呼びました。実際そのとおりなのです。
知識が増えただけなら蘊蓄を披露する回数が増えるだけですが、考え方や物の見方が変わったら、それまでうまく調和していた場(≒人のネットワーク)から外れることになります。
こういう風に記述すると、ちょっと怖さを感じてしまうかもしれません。それは自然な反応でしょう。やすやすとできることではない。それが自然にできるレアな人もいるでしょうが、自分が属する場からはじかれてしまうことに深いレベルで恐怖を感じることは多いかと思います。
だからこそ「場」が大切なのだ、と私は思います。
「最近、こういうことをに興味を持っているんです」
「へぇ〜、面白いですね」
という何気ないやりとりが行われる場は、「キモくなる怖さ」を緩和してくれるように思います。
もちろんその場はスペシフィックな、あるいなアドホックな場であることが望ましいです。言い換えれば、その場がその人の人生そのものにはならないこと。一時的・限定的にそこにいくけども、そこから帰っていく別の場もある。生活の場。そのような往還が、二次的な変化を呼び込みます。
そのような往還を繰り返す中で、自分自身を変えながら、同時により自分自身であり続けること。つまり、訂正可能性(BC106参照)が示す開きと綴じの可能性がそこにあるわけです。
This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit bookcatalyst.substack.com/subscribe -
面白かった本について語るPoadcast、ブックカタリスト。
今回は、『結婚の社会学』について語りました。たぶん、今までごりゅごが語った中で一番社会派の話です。
日常的にずっとこういうことを考えてる、ってわけではないし、常にこんな高尚な問題意識を持って生活してる、なんてことは全然ないんですが、人生の中で時々はこういうことを考える時間があった方が、長い目で見て豊かな生活を送れるのではないか。
そんなことは思います。
なによりも、本編でも語ってることなんですが、自分はまずこの本でかかれていたようなことをまったくもって「知らなかった」
人間、知らないことについて考えることはできません。
だからこそ、まず第一歩としてこういう考え方があるんだな、ということを知っておく。
これだけでも、今後の人生でなにかこの本の中身と関連するような出来事があった時の大きな判断の助けになるような気がしています。
今回出てきた本はこちらで紹介しています。
📖ブックカタリストで紹介した本 - ナレッジスタック - Obsidian Publish
This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit bookcatalyst.substack.com/subscribe -
今回は『訂正可能性の哲学』を取り上げました。
主に紹介したのは第1部の内容で、最後に少し倉下の考え(自己啓発の課題)も提示してあります。
本編は 07:30 あたりからスタート。倉下の読書メモは以下のページで確認できます。
◇ブックカタリストBC106用メモ | 倉下忠憲の発想工房
家族と思想
本書で一番ビビっときたのが、エマニュエル・トッドの家族と社会体制の関係を補助線にしながら、私たちは「家族」的なものの外側には出られないのではないか、と提示された部分です。
家族の外に出たと思ったら、そこにも家族があった。
フラクタルな構造としても面白いですし、私たちの思考・思想が生まれ育った環境に強く制約されているという点でも示唆に富む提示です。
その上で、です。
私たちたちが生まれ育つ環境そのものが動いている、という点も見逃せません。生活の実態として「家族」的なものが今後変化していくならば、私たちの共同体の思想もその土台から動いていくことが考えられます。おそらくそれは、希望を形作る可能性でしょう(もちろん、絶望に転じる可能性も同時にあるわけですが)。
たとえば、金田一蓮十郎の『ラララ』では、恋愛ではない形で結婚した夫婦が養子を迎え入れるという「家族」の形を提示していますが、そのようなさまざまな形態の家族が増えていけば、私たちの共同体思想も変わっていくのかもしれません。
訂正可能性
本書の中心となるのが「訂正可能性」であり、それは「閉じていながら、開いている」という二重の性質を持ちます。また、「訂正可能性」を持つためには、つまり「訂正される」という可能性を担保するためには、それが持続・継続していく必要があります。
開きと閉じの二重性、そして継続性・持続性。
そうした性質が大切だよ、ということを真理の追究や功利主義などとは違った立場から本書は提示してくれています。
ごく卑近な実感としてもその提示には頷けるものがあります。たとえばこの「ブックカタリスト」は、あるブックカタリストっぽさを維持して続けていくことが大切でしょう。ある日聴いたら「楽にめっちゃ儲けられる方法」などが語られていたら残念感が半端ありません。
一方で、そのブックカタリストっぽさは常に更新され続けていくことも必要です。同じでありながら、変化もすること。それがシンボル(ないしブランド)にとって重要な要素です。
それと共に、やっぱり配信を続けていくことも大切です。というよりも、同じでありながら、変化もすることは続けていくからこそ可能なのです。
単に続ければいいというものではないし、単に変化すればいいものでもないし、単に変わらなければいいものでもない。
これらの複合において、はじめて可能になるものがある。
そういう意味で、本書の提案は哲学的面白さ以上に、実践的活動において大切な話だと個人的には感じました。
This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit bookcatalyst.substack.com/subscribe -
いよいよ年末です。
今回も前回に引き続き一年間の配信を振り返ってみました。7月から11月までの配信の振り返りです。
2024年の配信(後半)
* 2024年07月02日:BC093「自分の問い」の見つけ方
* 2024年07月16日:BC094 『熟達論』
* 2024年07月31日:BC095『BIG THINGS』から考える計画問題
* 2024年08月13日:BC096 人間の色覚と色について
* 2024年08月27日:BC097『生産性が高い人の8つの原則』
* 2024年09月24日:BC098 『ATTENTION SPAN(アテンション・スパン) デジタル時代の「集中力」の科学』
* 2024年10月08日:BC099 論文を書くとはどういうことか
* 2024年10月22日:BC100ブックカタリスト・ビギンズ
* 2024年11月05日:BC101 『プリズナー・トレーニング』
* 2024年11月19日:BC102 積ん読の効能
* 2024年12月03日:BC103 『肥満の科学』
こうして振り返ってみると、7月からの倉下の紹介本はかなり「実用書」に偏っていたと思います。言い換えれば、思想・哲学的な話が少なかった印象。
ごりゅごさんも同様に、「体」の話が多かったですね。
こういうのはテーマ・リーディングというほど明確な目的意識がないにしても、なんとなくそうなっちゃうという感じがあります。そのときそのときの自分の勢いとか流れみたいなものが傾向をつくるわけですね。
そういう流れは、意識的に生み出すのもそう簡単ではないので、そういう波がやってきたら素直に乗ってみるのも一興だと思います。「そのとき読みたい本を読む」というのは、そういう駆動力を最大限に活かす読み方です。
というわけで、今年もありがとうございました。そして、来年からもよろしくお願いいたします。
This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit bookcatalyst.substack.com/subscribe -
いよいよ年の瀬です。
今回は一年間の配信を振り返ってみました。さすがに量が多いので、前後編に分けてお送りします。今回は前編で、1月から6月までの配信の振り返りです。
2024年の配信(前半)
* 2024/01/02:BC080『観光客の哲学』と『哲学の門前』から考える読書について
* 2024/01/16:BC081 『ピダハン』と『ムラブリ』から考える価値観への文化の影響
* 2024/01/30:BC082『思考を耕すノートのつくり方』から考えるノウハウのつくり方
* 2024/02/13:BC083 『ザ・フォーミュラ 科学が解き明かした「成功の普遍的法則」』と『残酷すぎる人間法則』の2冊から考える人間関係
* 2024/02/27:ゲスト回BC084 jMatsuzaki さんと『先送り0(ゼロ)』
* 2024/03/12:BC085『文学のエコロジー』から考える文学の効用
* 2024/03/26:BC086『体育館の殺人』から考える新しい読書について
* 2024/04/04:BC087 『音楽の人類史:発展と伝播の8億年の物語』
* 2024/04/23:BC088『CHANGE 変化を起こす7つの戦略』
* 2024/05/07:BC089『たいていのことは20時間で習得できる』と『成功する練習の法則』から考えるスキルを獲得するというマインドの獲得
* 2024/05/21:BC090『人生が整うマウンティング大全』と『話が通じない相手と話をする方法』から考える「話の聞き方」
* 2024/06/04:BC091『センスの哲学』
* 2024/06/18:BC092 『Mine! 私たちを支配する「所有」のルール』
全体として、脈絡がぜんぜんないような、それでいて何かしらの通奏低音は感じられるようなそんなラインナップでした。
たとえば、BC083の人間関係と、BC090のコミュニケーションの話はつながっています。加えて、BC088の人の行動に変化を与えるときに小さな集団に注目するという話も関係しているでしょう。もっと言えば、BC081の文化と価値観の話も、自分自身と所属している共同体との関係としても拡張できそうです。
そんな感じで、まったく同一のテーマの本ではなくても、「近場をうろうろする」ように読書をしていると新たなつながりが見えてくるものですし、それは「より大きな視点で捉えること」「自分なりのテーマを語ること」にもつながってきます。
というわけで、本を読むこととは本を読み続けることである、という倉下のテーゼが出てくるわけですが、それ以上に、自分が話したはずのことをぜんぜん覚えていないという体験は、読書に限らず年末に一年の振り返りをしているとたびたび起こる楽しい体験で、だからこそ積極的に記録を残していきたいなという気持ちが高まってきます。
皆さんも、ぜひ一年の活動の振り返りをやってみてください。
あと、「ブックカタリストの配信で、これが今年印象に残った!」といったコメントもお待ちしております。
This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit bookcatalyst.substack.com/subscribe -
面白かった本について語るPoadcast、ブックカタリスト。
今回は、プリズナー・トレーニングに続いての「運動・健康シリーズ」として『肥満の科学』について語りました。
前回紹介したプリズナートレーニングは、想像以上に多くの人が興味を持っていただけたみたいで、ごりゅごも仲間が増えてとても嬉しくなっています。
そして、自分の興味関心というのはやはり波があるもので、筋肉を付ける、強くなる、という部分に興味を持つと、そのまま似たようなことへのアンテナ感度が高まってきます。
で、今回のテーマは「肥満」です。人は、なぜ太るのか。そして、なぜ運動が重要なのか。
約2年前にも、なぜ太るのか。なぜ運動が重要なのか、という話は紹介しています。
BC056 『運動の神話(上)』 - by goryugo and 倉下忠憲@rashita2 - ブックカタリスト
BC060『運動しても痩せないのはなぜか』『科学者たちが語る食欲』
が、今回はこれとはまた違った観点での紹介であったところが面白い。
結果的には、どの本も同じようなことを言っているんだけれども、それぞれちょっとずつ、理由や、やることが違う。
結局のところ、人体は超複雑です。現代の科学で「すべてを解き明かす」なんてことはおそらく出来ないし、仕組みがすべて分かったとしても、ひとりの人間の認知の能力で、それを理解して、コントロールし切ることは不可能だろうな、とも思います。
と同時に、だからこそ人体の仕組みを知ろうとすることは面白いし、そこから学んだことを実践して「うまくいく」ときが面白い。
自分がこの分野に興味を持つ大きな理由は、そういう部分なのかな、と感じます。
今回出てきた本はこちらで紹介しています。
📖ブックカタリストで紹介した本 - ナレッジスタック - Obsidian Publish
This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit bookcatalyst.substack.com/subscribe -
今回のテーマは「積ん読の効能」。『積ん読の本』で語られていたことを眺めながら、本を積むこと、本棚に本を並べることについて考えます。
積ん読とは何か?
「積ん読」は、なんとなく意味がつかめる言葉ではありますが、本を読む生活を送っている人の感覚からすれば、「読むつもりはあるが、まだ読めていない」状態をさすことが多いようです。
辞書などのようにそもそも読了するような目的を持たない本が読み切られていなくても、それは──感覚として──積ん読とは呼ばないわけです。
言い換えれば、読もうと思って買ってはいるが、その思いがまだ達成されていないわけで、そこに罪悪感が発生する余地があるわけですが、その点を気に病んでいる方はほとんどいらっしゃいませんでした。そんなことを気にしていても埒が明かないということはたしかです。
では、なぜそんな状態が生まれてしまうのか。つまり、読もうと思って買っているのに、読めていないという「読書の渋滞」のようなことが生まれてしまうのか。
本書を読めば多方面からの分析が可能だとわかります。
* 本を読む経験が増えると、読みたい本が等比級数的に増える
* 新刊で見つけたうちに買っておかないと書店からなくなる
* 書店からなくなると「見えなくなる」ので本の存在自体を忘れる
* 絶版になれば入手も難しくなる
* 日常的に広告情報に触れているので「読もう、読みたい」と思える本の数が増えている
* 大人になると忙しくなるので本を読むための時間が減少する
以上のような複合的な要因で、読むスピード > 買う本の量 という「積ん読不等式」が成立してしまうわけです。
でも、たとえそうであっても構わない。その主張を補強する理由もさまざまなものが本書では見つけられます。
知のインデックス
そうした理由のうち、私個人として採用したいのが「知のインデックス」をつくるという山本貴光さんの意見です。何かしらの本があり、何某氏が書いており、何かしらの主張がなされている、ということがとりあえず自分の脳内に入っている。そういうインデックスができていれば、必要になったときにその本に手を伸ばすことができます。
現在ではほどんどの本の書誌情報はググれば見つけられますが、逆に言えばググらなければ出てきません。そして、脳内の発想はググらずに起こる現象なのです。自分の脳の奥深くに沈んでいるもの。別のメタファで言えば、記憶のネットワークに織り込まれているもの。それが「使える知識」であり、知のインデックスはその文脈において役立ちます。
そう考えると、私の知的関心はある本の中にどんな記述があるのかよりも、たとえばGTDとツェッテルカステンとPARAとメタ・ノートがあるとして、それらはどのような連関にあって、その連関から何が言えるのかを考えることにあります。いつ誰が、どのように論じてきたのか。そういう流れを踏まえることも大切にしたい。
そんな風にして「本々」(Books)を眺めようと思ったときに、本棚も「自分のノート」として使っていこうとする試みは、はたいへん面白いと感じました。
というわけで、私は「私の本棚」の運用についてヒントを得たわけですが、他の方は他の形で違ったヒントが得られる本だと思います。本の収集癖を強く持っていない方でも楽しめる一冊です。
This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit bookcatalyst.substack.com/subscribe -
面白かった本について語るPoadcast、ブックカタリスト。
今回は、プリズナー・トレーニングについて語りました。
ブックカタリストの配信回数も3桁に到達し、気分的には「ブックカタリスト2.0」というところ。
そのスタートに(個人的にはとてもふさわしいと思っている)本を運良くいいタイミングで紹介することが出来たな、と感じています。
ブックカタリストでこれまで紹介してきた本は大半が「真面目な本」だったんですが、ブックカタリストのテーマは「面白かった本について語るPoadcast」であり、それがマジメっぽい本であるとか、むずかしそうな本、賢そうな本であると言うこととはなんの関係性もないのです。
とは言え、100回も回数を重ねていると、どうしても方向性が固まってきてしまい、そこから外れた本を選びづらくなってしまうと言うのもまた事実。
101回の今回は、そこを打破する為にもいつもとはちょっと違う感じである、ということが重要だと感じていたのです。
とは言え、個人的には内容と言うか本編のノリ自体は基本的にほぼいつもと同じ感じにはなっていると思うし、なによりも今回の本はこれまでの「運動」「ダイエット」「練習」などといったテーマで紹介してきたブックカタリストの本の「実践編」みたいな見方も出来るわけです。
なによりも、実際にごりゅごはこの本を多いに楽しんで読めているし、読み終えてからも常に手元ですぐに読めるようにしていて、筋トレを行う前や後など、折りに触れてしょっちゅう何回も読み返しています。
「運動しないとなー」みたいな感覚はもう10年以上も持っていて、これまではずっと「健康の為にしゃーないから運動する」でした。
これが今はついに(大人になってから初めて?)楽しくて、やりたくて、自分自身で積極的に筋トレをする、ということができるようになりました。
諦めない気持ちというのは、わりと大事なのかもしれない。
今回出てきた本はこちらで紹介しています。
📖ブックカタリストで紹介した本 - ナレッジスタック - Obsidian Publish
This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit bookcatalyst.substack.com/subscribe -
記念すべき第百回は、いつもと趣向を変えて二人の読書の略歴を語ってみます。
二人が紹介した本は
……。
出てきた本をぜんぶ列挙しようとしたんですが、あまりに数が多くなったのであきらめました。
倉下は赤川次郎『三毛猫ホームズの推理』からスタートするミステリ系統を出発に、神坂一『スレイヤーズ!』から始まるライトノベル・SF・異世界転生もの系統、野口悠紀雄 『「超」勉強法』から始まるノウハウ・自己啓発系統、村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』から始まる文学・ハードボイルド系統が、青年期の読書を構成していました。
事前のメモではそれくらいでだいたいカバーできていると思ったのですが、大学時代はプログラミング言語の本を読み漁っていましたし、コンビニ店長時代では経営学・経済学の本にも手を伸ばしていました。これらも系統ではあるでしょう。かなり多岐にわたっています。
ごりゅごさんはむしろもっと限定的で『三国志』ものを契機に歴史物を中心に読んでおられて、途中潜伏期間があった後、Obsidianによるノーティング技術の向上およびブックカタリストのスタートを契機にして再び読書欲が盛り上がってきたというお話でした。
その一つの契機に「インターネットが未来をワクワクさせてくれるというビジョンがあった」という話は非常に印象的だと感じます。人を本を読む気にさせるものは、やはりそういうワクワク感なのでしょう。「知的好奇心」と言ってしまうとあまりにも漠然としますが、読書というのは平静・冷静な知的活動ではなく、ある種のワクワク感に駆動されるドライブなのだと思います。
読書に歴史あり
そんな風にそれぞれの人にはそれぞれの読書の経歴があります。歴史と呼んでもよいでしょう。
私が今、一冊の本と対峙するとき、その背後には常に私の歴史が蠢いています。その本を読みたいと思うかどうか、読んだ後どう評価するか。そうした反応は歴史に由来するわけです。
だから同じ本でも読みたいと思うかどうか、面白いと思うかどうかは人によって違ってきます。個性による違いというよりも、歴史による違いなのです(あるいは、個性とはそれぞれの人の歴史である、とも言えるでしょう)。
広義で言えば、読書はたしかに「インプット」な活動です。でも、その表現では「歴史」の感覚が立ち上がってきません。均質的ではなく、個別的な活動。一度きりではなく、連続性のなかにある活動。それが読書です。
だから、「本を読むことは、本を読み続けることである」なんてことが言えるかもしれません。
ぜんぜん関係ないですが
二人の読書の歩みはまったく違っているのに、人生の歩み方においてすごく重なる部分があることが今回わかりました。
しかし、考えてみれば、本当になにもかもがまったく違っているならば、こうして二人でポッドキャストをしていることはなかったでしょう(政府が命令して無作為に選んだ二人にポッドキャスト運営を強制しないかぎりは)。重なる部分があるからこそ、活動を同じくしている。でも、多くの部分で違いがある。
たぶん組み合わせというのは、そういう感じのときうまくいくんじゃないかな、なんて思います。
皆さんも自身の読書のヒストリーを振り返り、自分のヒストリーで語ってみてはいかがでしょうか。
ご意見・ご感想はコメントおよびTwitter(現X)、Blueskyのハッシュタグ#ブックカタリストにてお待ちしております。
では、今後もブックカタリストをよろしくお願いします。サポータープランへのご加入も、ご検討くださいませ。
This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit bookcatalyst.substack.com/subscribe -
今回は「論文を書くとはどういうことか」をテーマに、論文についての二冊の本を紹介しました。
* 『論文の書きかた (ちくま学芸文庫 サ-55-1)』
* 『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』
それぞれ独自の魅力を持つ二冊です。
書誌情報
『論文の書きかた (ちくま学芸文庫 サ-55-1)』
* 著:佐藤健二
* 佐藤 健二(さとう・けんじ):1957年、群馬県生まれ。東京大学大学院社会学研究科博士課程中途退学。東京大学名誉教授。博士(社会学)。専攻は、歴史社会学、社会意識論、社会調査史、メディア文化など。著書に、『読書空間の近代』(弘文堂)、『風景の生産・風景の解法』(講談社選書メチエ)、『流言蜚語』(有信堂高文社)、『歴史社会学の作法』(岩波書店)、『社会調査史のリテラシー』など。
* 出版社:筑摩書房
* 出版日:2024/5/11)
* 目次
* 第1 章 論文とはなにか
* 第2 章 「論」と「文」の結合
* 第3 章 〈文〉で論ずることの厚み
* 第4 章 主題・問題意識・問題設定
* 第5 章 通念の切断と思考の運動
* 第6 章 観察と対話の組織化
* 第7 章 調査研究のさまざまな局面
* 第8 章 2 項対立のあしらいかた
* 第9 章 リレーショナル・データベースとしての社会
* 第10 章 「クダンの誕生」の経験をふりかえる
* 第11 章 リテラシーの発見
* 第12 章 読書空間のなかで書く
* 第13 章 コピペと引用の使いこなし
* 第14 章 見えかたをデザインする
* 第15 章 研究倫理の問題
* 第16 章 編集者として見なおす
『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』
* 著:阿部幸大
* 日本の文学研究者。筑波大学人文社会系助教(2024年時点)。北海道出身。
* 出版社:光文社
* 出版日:2024/7/24
* 目次
* 原理編
* 第1章 アーギュメントをつくる
* 第2章 アカデミックな価値をつくる
* 第3章 パラグラフをつくる
* 実践編
* 第4章 パラグラフを解析する
* 第5章 長いパラグラフをつくる
* 第6章 先行研究を引用する
* 第7章 イントロダクションにすべてを書く
* 第8章 結論する
* 発展編
* 第9章 研究と世界をつなぐ
* 第10章 研究と人生をつなぐ
* 演習編
『論文の書きかた (ちくま学芸文庫 サ-55-1)』
本書は「論文を書くとはどういうことか」をさまざまな角度から論じていく一冊で、その場しのぎに論文を書き上げるためのテクニックではなく、研究活動の一環に論文の執筆をおき、その中でいかに研究を進めるのか=論文を書くのかが検討されていきます。
重厚な論述であり、著者の思考が垣間見れる面白さもあり、話題が枝葉のように広がっていて、それらがいちいち楽しめる魅力も持ち合わせています。
個人的には「文」に注目した論考が心に残りました。自分なりにまた展開させていきたいと感じます。
『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』
きわめてテクニカルでプラクティカルな一冊。それでいて著者の熱さも伝わってきます。「まったく新しい」という看板に偽りはありません。
一冊目の本に比べると重厚な論述感は小さいものの、シャープで説得的な論考は一気に引き込まれます。でもって、アドバイスが非常に役立つ。学術寄りの知的生産を行うなら必携の一冊でしょう。
こちらも単に表面的なノウハウを提示して終わりにするのではなく、論文を書くときに必要な「頭の使い方」を提示してくれている点が魅力です。
個人的には、本編でも語ったようにアカデミックではないライティングの方向性を検討してみたいと思います。
This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit bookcatalyst.substack.com/subscribe -
面白かった本について語るPoadcast、ブックカタリスト。
今回は、『ATTENTION SPAN(アテンション・スパン) デジタル時代の「集中力」の科学』について語りました。
スマホの登場によって、私たちにどんな変化が起こっているのか。
iPhoneが出たばかりの頃の自分は、それによるよい変化にしか注目していませんでしたが、最近はそこから起こる「よくないこと」にも注目するようになってきました。
特に、スマホという「最強の暇つぶしツール」を手に入れた我々は、いつのまにかほんのわずかな時間の退屈を耐えることができなくなり、結果的にこれまで以上に「退屈」という問題に悩まされるようになっている。
そんな問題意識を持って、この本を読んだ印象です。
自分が変わったなあ、と思うのは、こういう「〜について考えるためにこの本を読もう」みたいな観点で本を選ぶことができるようになった、ということです。
自分の読書力が上がったかどうかは、客観的に評価する手段はないんですが「気になってることを考えるために本を読む」ことがきちんと言語化できるようになったというのは、明確に進歩だと思います。
これは、ちゃんと他人に誇れる変化。
なんだかんだもう、100回近くもずっと本について話してたら、なにか変化はあるよね。それを身をもって体験できたことは大きいです。
ブックカタリスト100回記念イベント
というわけで、詳細はまたお送りする予定ですが、まもなく到達するブックカタリストの100回を記念して、東京のどこか(東京駅近辺の予定)で、100回到達記念イベントを行う予定です。
テーマは「ブックカタリストの語り方(仮)」
開催日は、11月17日の午後から夜にかけて。
詳細が決まり次第、またご連絡いたします!
今回出てきた本はこちらで紹介しています。 📖ブックカタリストで紹介した本 - ナレッジスタック - Obsidian Publish
This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit bookcatalyst.substack.com/subscribe -
今回はチャールズ・デュヒッグの『生産性が高い人の8つの原則 (ハヤカワ文庫NF)』を取り上げました。
いわゆる「ライフハック」な考え方がたっぷりな一冊です。
書誌情報
* 原題
* SMARTER FASTER BETTER: the secrets of being productive in Life and Business(2016/3/8)
* 単行本版
* あなたの生産性を上げる8つのアイディア 単行本 – 2017/8/30
* 著者
* チャールズ・デュヒッグ
* ジャーナリスト。イェール大学卒業後、ハーバード・ビジネス・スクールにてMBA取得。「ロサンゼルス・タイムズ」「ニューヨーク・タイムズ」のライターを務め、現在は「ニューヨーカー・マガジン」その他に寄稿。2013年には「ニューヨーク・タイムズ」のリポーターのチーム・リーダーとして、ピュリッツァー賞(解説報道部門)を受賞。最初の著書『習慣の力〔新版〕』(ハヤカワ・ノンフィクション文庫)は「ニューヨーク・タイムズ」のベストセラー・リストに3年間も留まった。第2作である本書も2016年、同リストにランクインした。
* 翻訳
* 鈴木晶
* 『愛するということ』、『猫に学ぶ――いかに良く生きるか』、『ラカンはこう読め! 』など多数。
* 出版社
* 早川書房
* 出版日
* 2024/3/13
* 目次
* 第1章 やる気を引き出す―ブートキャンプ改革、老人ホームの反乱と指令中枢
* 第2章 チームワークを築く―グーグル社の心理的安全と「サタデー・ナイト・ライブ」
* 第3章 集中力を上げる―認知のトンネル化、墜落したエールフランス機とメンタルモデルの力
* 第4章 目標を設定する―スマートゴール、ストレッチゴールと第四次中東戦争
* 第5章 人を動かす―リーン・アジャイル思考が解決した誘拐事件と信頼の文化
* 第6章 決断力を磨く―ベイズの定理で未来を予測(して、ポーカーに勝つ方法)
* 第7章 イノベーションを加速させる―アイディア・ブローカーと『アナと雪の女王』を救った創造的自暴自棄
* 第8章 データを使えるようにする―情報を知識に変える、市立学校の挑戦
* 付録―本書で述べたアイディアを実践するためのガイド
「生産性を高める」とは
インターネットの仕事術系情報では「生産性向上」や「productivity」といった言葉をよく見かけるわけですが、そのたびに私は「むむっ」と警戒フィルターを発動させます。
というのも、単にそれが「タスクをたくさんこなすこと」を意味しているのではないか、あるいは生産性向上のためのツールを使うことそのものが目的になっていないか、という懸念があるからです。
実際、一時間のうちに実行できるタスクが10から20に増えたとしても、そのタスクが効果を上げていないことは十分ありえるでしょうし、タスク以外の目を向けるべきものから目を逸らしてしまっていることもあるでしょう。はたしてそれは望ましい「改善」と言えるのでしょうか。
一方で、たしかに効果的(エフェクティブ)な状態というのはあって、メールを書こうとして、なかなか取り掛かれずに、インターネットを彷徨っている間に、新しいツールの情報を見かけて喜び勇んでダウンロードしてしまっている、という状態はあまり効果的な時間の使い方ではないとは言えるので、何一つ改善を試みようとしないというのも、それはそれで違う気がします。
本書では、「生産性を高めるのに必要なのは、今よりももっと働き、もっと汗を流すことではない」という明瞭な指針が掲げられていて、「まさにその通り」と強く感じられます。
以下のような定義も登場しますが、
* 最少の努力で、最大の報いが得られる方法を見つけること
* 体力と知力と時間をもっと効率よく用いる方法を発見すること
* ストレスと葛藤を最小限にして成功するための方法を学習すること
* 大事な他のことをすべて犠牲にすることなく、何かを達成すること
これに納得できる人もいれば、そうでない人もいるでしょう。
それでも「生産性とは、いくつかの方法を用いて正しい選択をすることである」という根本的な方向性については同意できるのではないでしょうか。
さらに言えば──本編でも語っている通り──、「正しい選択をするために、自分は有効な方法を使っている」という感覚を持つことが、人生全般にわたる「やる気」の高め方なのかもしれません。This is Lifehacks.
This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit bookcatalyst.substack.com/subscribe -
面白かった本について語るPoadcast、ブックカタリスト。
今回は、人間の色覚と色について語りました。(『見たい! 聞きたい! 透明水彩! 画家と化学者が語る技法と画材』、『ひとの目、驚異の進化: 4つの凄い視覚能力があるわけ』をメイントピックにしつつ、わりとフリーで語った感じです)
お絵かきというものを始めてみて一番面白かったのは、今回のような「お絵かきをしなかったら絶対興味を持たなかったであろうこと」にも興味を持つことが出来たことです。(お絵かきをしなかったら「絵の具ってどういうものなんだろう」なんてことを考える人はまずいないですよね?)
世の中のありとあらゆることって「知ってる」と「やってる」にはとてつもなく大きな壁があって、これを乗り越えた数が多ければ多いほど、多くのことに興味関心を持てるようになるのではないか、と感じます。
で、この「知ってる」と「やってる」って、最初の一歩は本当にめちゃくちゃ小さな違いでしかないんですよね。
半歩踏み込んで、ちょっとだけ試してみる。これができるだけで、数週間、数ヶ月後には、技術だけでなく、世界の見え方にもめちゃくちゃ大きな差が生まれてくるのではないかと思います。
ごりゅごは最近世界の「色の見え方」がけっこう変わった感じがして、これまでより1段階、世界を見ることが楽しくなりました。
以下、要約です。
話題: 色覚と絵画の科学的・進化論的視点
* 色と絵画の科学的視点
* 水彩画に関する技法や画材について紹介
* 色相、彩度、明度など色の基本的な概念の説明
* 水彩絵具の化学的背景、特に顔料と染料の違いについて
* 絵具の色が変わる要因(粒子の大きさや混色)について
* 絵画における色の選択や新しい色彩の開発についての話題
* 人間の色覚と進化
* 人間の色覚が進化した背景として、食物の識別だけでなく、肌の色の変化を見分ける能力が重視された可能性
* 肌色の変化を見分けることが、コミュニケーションや社会的協調性において重要であったこと
* 四季覚異常が男性に多い理由とその進化論的説明
* 色覚の進化に伴う顔の毛の減少とその影響
* 進化論と社会的影響
* 肌色の違いが進化論的にあまり変わらないこと、しかし人間はそれを非常に敏感に感じ取ること
* 現代社会における肌色の違いが持つ社会的問題
* 人種間の肌色の違いの理解とその文化的影響について
* VRやテキストコミュニケーションにおける表情や肌色の非依存性とその可能性
今回出てきた本はこちらで紹介しています。
📖ブックカタリストで紹介した本 - ナレッジスタック - Obsidian Publish
This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit bookcatalyst.substack.com/subscribe -
今回は、『BIG THINGS どデカいことを成し遂げたヤツらはなにをしたのか?』を取り上げました。
書誌情報
* 著者:
* ベント・フリウビヤ
* 経済地理学者。オックスフォード大学第一BT教授・学科長、コペンハーゲンIT大学ヴィルム・カン・ラスムセン教授・学科長。メガプロジェクトにおける世界の第一人者
* デンマーク女王からナイトの称号を授けられた。
* 『建築家フランク・ゲーリーのプロジェクトマネジメント DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー論文』
* ダン・ガードナー
* カナダ在住のジャーナリスト、作家
* 『専門家の予測はサルにも劣る』
* 『超予測力 不確実な時代の先を読む10カ条』
* 翻訳:
* 櫻井祐子
* 『時間術大全――人生が本当に変わる「87の時間ワザ」』
* 『1兆ドルコーチ――シリコンバレーのレジェンド ビル・キャンベルの成功の教え』
* 出版社:サンマーク出版
* 出版日:2024/4/24
* 目次
* 序章「"夢のカリフォルニア"」
* 1章 ゆっくり考え、すばやく動く
* 2章 本当にそれでいい?
* 3章 「根本」を明確にする
* 4章 ピクサー・プランニング
* 5章 「経験」のパワー
* 6章 唯一無二のつもり?
* 7章 再現的クリエイティブ
* 8章 一丸チームですばやくつくる
* 9章 スモールシング戦略
* 終章 「見事で凄いもの」を創る勝ち筋
* 主題
* 私たちはプロジェクトをどのように進め、そしていかに失敗するのか。それを回避するにはどうしたらいいか?
* ビジョンを計画に落とし込み、首尾よく実現させるには?
プロジェクトはたいていうまくいかない
本書において重要な指摘は、プロジェクトというのはたいていうまくいかず、しかもそのうちの一部は破滅的な結果を引き寄せるくらいにうまくいかない、という点です。
そうした結果を引き寄せる要因には、権力(政治)と心理バイアスの二つがあって、私が注目したのは心理バイアスの方です。
私たち人間は、最初に思いついたことを素晴らしいアイデアだと思い込み、そのアイデアについて詳細な検討も、メタな分析もすることなく「計画」を立ててしまう。
実際その「計画」は、こうなったらいいなという妄想を並べただけのものであり、その通りに実現できなことは始めから決まっている。
ここで重要なのは、計画通りに実行できない主体が悪いのではなく、そもそもの計画立案が杜撰だ、という見方です。よく、自己啓発界隈でも計画を立てても、その通りに実行できない自分に罪悪感を覚えるという話を聞きますが、その見方はひっくり返した方がよいでしょう。
実行する主体(としての自分)が悪いのではなく、実行しうる計画を立てられていない主体(としての自分)が拙いだけなのです。*そもそも日本では上意下達の感覚が強いので、こういう見方に不慣れな人が多いのかもしれません。
で、実行しうる計画というのはシミュレーションが行き届いた計画であり、それは経験を織り込んだ計画とも言え、つきつめるとタスクシュートのようなログベースの"計画"だということになるでしょう。
計画の精度を突き詰めていくと、ログになる。
これは面白い話だと思います。
This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit bookcatalyst.substack.com/subscribe -
面白かった本について語るPoadcast、ブックカタリスト。
今回は、『熟達論:人はいつまでも学び、成長できる』について語りました。
この本は、「デジタルノートの熟達」というごりゅごが今ずっと考えているテーマに見事に刺さるものでした。
これは思いっきり自分に引きつけた話になるんですが、なにかを「練習して身に付ける」ことの大切さというのは、スポーツや芸術に限った話ではない、というのを改めて感じました。
最近はずっとObsidianというデジタルノートを「どうやって役立たせるか」ということばかり考えてるんですが、それも結局ある程度は練習して身に付けるしかない。
そして本で書かれていた5つの習熟の段階というのは、人になにかを教える時の手順においても参考になる本でした。
結局、大事なのは一番最初の「遊ぶ」部分。
どんな技能にしても、これができるかどうか。その部分こそが「才能」という言葉で適当に誤魔化されてしまっている、熟達の本質なんだろうな、ということを思った次第です。
以下、要約です。
* 今回の本
* 第94回のテーマ:『熟達論:人はいつまでも学び成長できる』
* タメスエ大さん著の本を取り上げる
* あいさつと前回の話題に関する余談
* 前回の余談:旅行の荷物準備の楽しさ
* Twitterでリスナーが「旅行の荷物を準備するのが楽しい」と共感
* 「過不足なく荷物が足りたことが嬉しい」
* 部屋の整理には興味がない
* パーソナリティたちの反応
* 情熱の方向性は個人差があるが、共通点も存在する
* 1000人に1人くらいは同じ趣味を持つ人がいるかもしれない
* 旅行荷物準備のコミュニティについての話
* アメリカの巨大掲示板「Reddit」にも関連するコミュニティがあるかもしれない
* 「旅行の荷物準備」に関心を持つ人はもっと多いかもしれない
* 本の紹介
* 『熟達論』は2023年7月に新潮社から出版
* タメスエ大さんの背景
* 陸上選手として400mハードルで世界選手権メダリスト
* 一般的な競技者とは異なるアプローチを取ってきた
* 引退後、競技や熟達に関する知識をまとめた本を書いた
* 本の内容とその共感部分
* 学びの方法が頭だけでなく身体でも覚えることに重点を置いている
* 自分の経験や取り組みに重なる部分が多い
* 例:アトミックシンキングやデジタルノートの使い方
* 学びの方法が学校の試験以外の生活全般に応用できる
* 熟達論の5段階
* 遊
* 主体的に行う、面白さが伴う、不規則である
* 例:設定をいじる、いろんなボタンをクリックするなど
* 最初に基本を教えるよりもまずは「遊ぶ」ことが大事
* 型
* 基本の型を覚える
* 例:片足で立つ、デイリーノートに何でも書く
* シンプルで検証が多分視されず、効果が期待されすぎない
* 型を覚えた上で試行錯誤を重ねる
* 型が良いか悪いかを見極めるポイント
* シンプルではないこと
* 検証が多分視されていること
* 効果が期待されすぎていること
* 観
* 観察し、パターンを見出す
* 量をこなすことで行動の境目やパターンが見えてくる
* 自分にとって役立つものや不要なものが分かるようになる
* 分ける行為に必ず取りこぼしがある
* 完璧を目指さず、試行錯誤を続けることが重要
* 心
* 中心を知り、それを基に冒険ができる
* 基準があることで冒険ができる
* 例:手足の動きが中心に支えられる
* 個別性が重要であり、全員に同じ最良の方法は存在しない
* 空
* 無心になり、行為のみがある状態
* 考えずに身体が勝手に動く
* 時の流れが違うように感じる
* 思い込みの中でしか思考できないことを自覚する
* 勘を尊重する
* 行為のみがある状態は仏教的なニュアンス
* その他のポイント
* 苦しいことと成果が結びつかないこと
* 効率の良い練習が重要
* 努力が報われるとは限らない
* 言われた通りにやるだけでは止まってしまう
* 自分の個別性を考慮することが大切
* 練習時間よりも集中の濃淡とリズムが大事
* 量より質が重要
* 環境を整えることも練習の一環
* 人間の特性として環境に適応する力が強い
* イメージによる動作の導き方
* 例:ハードルを飛ぶときのイメージ
* 著者の思い
* 宮本武蔵の『五輪書』の現代版を目指したい
* 競争と学びの違い
* 競争は勝ち負けがあるが、学びは全ての人に開かれている
* 学びを娯楽化することが熟達への道
* 学びを楽しむことが最も重要
今回出てきた本はこちらで紹介しています。
📖ブックカタリストで紹介した本 - ナレッジスタック - Obsidian Publish
This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit bookcatalyst.substack.com/subscribe -
今回は、以下の二冊を取り上げながら「自分」を知るための方法について考えていきます。
* 『リサーチのはじめかた ――「きみの問い」を見つけ、育て、伝える方法 (単行本)』
* 『人生のレールを外れる衝動のみつけかた (ちくまプリマー新書 453)』
書誌情報
『リサーチのはじめかた』
* 著者
* トーマス・S・マラニー
* スタンフォード大学歴史学科教授。コロンビア大学で博士号を取得。専門は中国史。邦訳書に『チャイニーズ・タイプライター』(2021年、中央公論新社)がある。BBCやLA Timesなどで研究が取り上げられるほか、Google、Microsoft、Adobeなど企業での招待講演も多数。
* クリストファー・レア
* ブリティッシュ・コロンビア大学アジア研究学科教授。コロンビア大学で博士号を取得。専門は近代中国文学。著書にChinese Film Classics, 1922-1949などがある。
* 翻訳:安原和見
* 出版社 筑摩書房
* 出版日:2023/9/1
* 目次
* 第 1 部 自 分 中 心 の 研 究 者 に な る
* 第1章 問いとは?
* 第2章 きみの問題は?
* 第3章 成功するプロジェクトを設計する
* 第 2 部 自 分 の 枠 を 超 え る
* 第4章 きみの〈問題集団〉の見つけかた
* 第5章 〈分野〉の歩きかた
* 第6章 はじめかた
『人生のレールを外れる衝動のみつけかた (ちくまプリマー新書 453)』
* 著者:谷川嘉浩
* 1990年生まれ。京都市在住の哲学者。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了。博士(人間・環境学)。現在、京都市立芸術大学美術学部デザイン科講師。哲学者ではあるが、活動は哲学に限らない。個人的な資質や哲学的なスキルを横展開し、新たな知識や技能を身につけることで、メディア論や社会学といった他分野の研究やデザインの実技教育に携わるだけでなく、ビジネスとの協働も度々行ってきた。著書に『スマホ時代の哲学――失われた孤独をめぐる冒険』(ディスカバートゥエンティワン)『鶴見俊輔の言葉と倫理――想像力、大衆文化、プラグマティズム』(人文書院)、『信仰と想像力の哲学――ジョン・デューイとアメリカ哲学の系譜』(勁草書房)。
* 出版社:筑摩書房
* 2024/4/10
* 目次
* 序 章 なぜ衝動は幽霊に似ているのか
* 第一章 衝動は何ではないか
* コラム 否定神学、他人指向型、『葬送のフリーレン』
* 第二章 衝動とは結局何ものなのか
* コラム 言語化のサンクコスト
* 第三章 どうすれば衝動が見つかるのか
* コラム 「それっぽい説明」から逃れるには
* 第四章 どのようにして衝動を生活に実装するのか
* コラム 観察力の重要性 ― 絵画観察のワークショップからOODAループまで
* 第五章 衝動にとって計画性とは何か
* コラム 社会的成功と結びつけない
* 第六章 どうすれば衝動が自己に取り憑くのか
* コラム 衝動の善悪を線引きすることはできるか
* 終 章 衝動のプラグマティズム、あるいは実験の楽しみ
本編ではそれぞれの本の序盤部分を取り上げ、自分が持つ問題意識や衝動にせまる必要や、その方法について紹介しました。
実際の本はさらに多くの内容が展開されているので、ご興味を持たれたら実際にお読みになることをお勧めします。
本編のときに使ったメモは以下からご覧いただけます。
◇ブックカタリストBC093用メモ - 倉下忠憲の発想工房
「自分」の研究
私は「ノウハウ」に興味があります。知識の具体的運用。その際に問題になるのは、「自分は何がしたいのか」「自分は何が好きなのか」という要件です。この情報がまるっと抜け落ちていたら、どのようなノウハウも効果を発揮しないでしょう。
逆にその点を理解していれば、あまたのノウハウを自分に合わせて使っていくことができますし、場合によっては新しく創造することも可能でしょう。
つまり、「ノウハウ」という情報資産を活用する上で、「自分のこと」を知っておくのは大切なわけです。そこで、そうした営みを「セルフスタディーズ」と呼び、これまでずっと考え続けてきました。そこで出会ったのが本書らです。
ポイントは、「自分」というものを既知で十全に把握している対象ではなく、むしろ流動的でつかみ所がなく、そのすべてを把握することは不可能な対象とすることです。そうした対象であるからこそ、「研究」してみようと思えるわけですから、この視点の切り替えはきわめて大切です。
どちらの本でも、ただ思弁的に「考える」のではなく、さまざまに「実験」してみること推奨しています。むしろ、私の考えでは思弁的に考えれば考えるほどわからなくなるのが「自分」という対象なのでしょう(むしろそれは現象と呼ぶべきかもしれません)。
デジタルツールにおいても、このツールで自分が何をしたいのかと考えてみても即座に答えが出るものではありません。実際にいろいろやってみることが必要です。一方で、「ただやればいい」というものでもない。いろいろやりながら、それと並行して「自分は何をしたいのか」と考えること。その中で、「うん、これはいい感じがする」「これはちょっと違うな」と自分の反応を観察していく。そういう道行きが大切なのでしょう。
でもって同じことが、生きること全般に言えると思います。
「生きることで、自分を知る」
まとめるとそんな感じになるでしょうか。
This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit bookcatalyst.substack.com/subscribe -
面白かった本について語るPoadcast、ブックカタリスト。
今回は、『Mine! 私たちを支配する「所有」のルール』について語りました。
久しぶりに「すごく熱中してすごくしっかり読んだ」という感じの本で、決して内容が難しいわけではないけれども、考えさせられることがめちゃくちゃたくさんある本でした。
雑な説明をすれば「所有ってなんなのか」ということを通じて、社会や人間を考えていこうみたいな話、というので終ってしまいます。ただ、本に書かれている事例の多くのことが「そういう風に考えたことなかった」というものが多く、知識というよりもたくさんの新しい視点を知ることが出来た、という感覚でした。
最近のブックカタリストはわりと昔に読んだ本を、脳内で整理できてるから語る、という漢字の内容が多かったんですが、今回は「めっちゃ面白かったから熱いうちに語りたい」というタイプのもの。
どっちがよりよい方向性なのかは簡単に答えは出ないんですが、まあそういうのを好きなように、楽しんで語れてる、という姿勢が一番重要なのかな、と思うので、そこらへんはこれからも「面白いと思った本」について語っていく、という姿勢で続けていきます。
以下、要約です。
* 本の紹介と著者について
* 紹介する本は「マイン - 私たちを支配する所有のルール」
* 2024年3月に早川書房から出版
* 著者はマイケル・ヘラー、所有権に関する世界的権威
* マイケル・ヘラーは不動産法を担当する大学教授
* 以前に「グリッドロック経済」という本も執筆している
* 所有権の概念とその重要性
* 所有権のルールは根拠をめぐるストーリーの戦い
* 所有権に関する様々な事例や理論が紹介される
* 具体的な事例と議論
* 飛行機のリクライニングシート問題
* リクライニングシートを倒す権利は誰にあるのか?
* 付属の権利:アームレストのボタンがリクライニングを許可するという考え方
* 占有の権利:もともとシートが直立していた空間はその人のものであるという考え方
* 早い者勝ち:シートを倒せなくするマシーンを早く設置した人が優先される
* 航空会社の責任:座席を二重販売しているとも言える
* アメリカの裁判の傍聴権
* 行列代行業者の存在
* 裕福な人が行列に並ばずに権利を購入する問題
* 早い者勝ちが資本主義によって歪められている例
* 大学のバスケットボールの試合のチケット取り
* チケットを取るために48時間キャンプを張って並ぶ
* 忍耐力競争としての行列
* 卒業後の寄付金制度によるチケット権利の獲得
* ディズニーのファストパス制度
* 待ち時間を減らすことで収益を増やす仕組み
* ファストパスからビップツアーへの進化
* 一般の人々が納得する仕組みの工夫
* 希少な資源をうまくコントロールすることでビジネスとして成功する
* 所有権の根拠となる6つの概念
* 早い者勝ち:先に取ったものがその人のもの
* 占有:自分がいた場所だから自分のもの
* 労働の報い:自分が働いて得たものは自分のもの
* 付属しているもの:自分の所有物に付随するものも自分のもの
* 自分の体:自分の体は自分のものだと言えるかどうか
* 家族のもの:家族のものは自分のものだと言えるかどうか
* 文化や社会的信頼の影響
* 所有権の概念は文化によって異なる
* 所有権争いがいかに大変かを示す事例
* スーパーでのカートの所有感覚の例
* カーネマンの実験:戦友効果が所有権の感覚を生む
* 現代社会における所有権の問題
* 著作権や特許の問題
* 権利の複雑化とその影響
* キング牧師の「I Have a Dream」演説の著作権問題
* 映画や音楽の権利が複雑化し、創造性を阻害している例
* 基礎研究の特許問題:複数の権利が絡み合い新しい薬の開発が進まない
* ファッション業界の例:著作権が存在しないが創造性が保たれている
* Linuxやオープンソースの成功例:著作権フリーで収益を上げる
* 結論
* 所有権のルールは絶対的なものではなく、常に変わり続ける
* 著者は所有権に関する問題を解決するためのヒントを提供
* ディズニーやオープンソースのような新しいビジネスモデルが示すように、所有権の問題には多様な解決策がある
今回出てきた本はこちらで紹介しています。
📖ブックカタリストで紹介した本 - ナレッジスタック - Obsidian Publish
This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit bookcatalyst.substack.com/subscribe - Visa fler